日本語源
○アイガモ
カモ×アヒルでアイガモ、鴨のいない季節の意。
○あこう鯛
カサゴの一種、赤魚鯛。
○あこぎ・阿漕
三重阿漕浦のこと、伊勢神宮献上用の神聖な海で、平治(平次)が病気の母親に食べさせようと密漁を繰り返した。
○あべかわ餅
徳川家康が「安倍川餅」と命名したとも。
※慶長年間徳川家康が笹山金山を訪れたおり出された「安倍川の金な粉もち」が気に入り、安倍川地方の名物となった。
○あみだくじ
阿弥陀くじ、古くは後光のごとく放射状の線だった。
※平等なので阿弥陀との説もある
○アメンボ
アメは飴、飴の香りがするので飴坊。
○あんことソップ・相撲
{あんこ}は魚のアンコウ、ソップはスープ(soup)、スープは鶏ガラなので骨だけ。
○いかもの食い
それを食べるのは如何がなものか、の意。
○一石橋・壹石橋
橋の両側に住んでいたのが後藤庄三郎と後藤縫殿助、後藤+後藤→五斗+五斗→一石。
○インドリンゴ
1975年青森東奥義塾のジョンイングが、故郷アメリカ・インディアナ州から種を持ち込んだ。
○うるう年
閏年を潤年と間違えたとの説がある。
○えこひいき
依怙贔屓。
○おくび
ゲップのこと。
○おとぎ話
古く「とぎ」は話し相手の意、戦国時代に殿様の相手をしたのが「御伽衆」。
○オニヤンマ
ヤンマはトンボの古称、四枚の羽が飛ぶと八枚に見えるので「八重羽」、訛って「ヤンマ」。
○オムレツ
omeは男(homme)、letteは小さいの意。
○お鉢が回ってくる
昔は、大勢で食事をするさい、お鉢(飯櫃)を順番に回し・自分でお鉢から茶碗にご飯をもった。
○カーキ色
ヒンズー語で土埃・塵の意、1848年インド駐留のイギリス陸軍が採用した。
○かきいれ
大福帳に売り上げを書き入れるが意。
○カモシカ
ウシ科の動物、古くはカモシシ。
○かやくご飯
加薬は薬味のこと。
○カルボナーラ
カーボン・Carbonが源。
○かん高い
甲高い音、邦楽で乙音(基音)に対して1オクターブ高い音(倍音)。
※「オツだね」もこれ(乙音)からきている。
○九州
筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向・大隅・薩摩。
○くだを巻く
「くだ」は糸巻き機の軸部分にある管、ブーンブーンと音を鳴らし続けることが源。
○グッドバイ
good-by、古くはGod be with you。
○グランドスラム
コントラクトブリッジの手、slamは戸などをピシャリと閉めるの意。
○ぐれる
「はまぐり」を逆に「ぐれはま」が転訛、ぴったり合わさる蛤を逆さにすると合わなくなるが源。
○クローバー
和名シロツメクサ(白詰草)、江戸時代にオランダからのガラス製品の保護クッション(隙間詰物)として使われていた。
○ケチを付ける
怪事が訛ってケチ、おかしなこと・けしからぬことが源。
○げんなおし・験なおし
縁起を逆さに読んでギエン→ゲンともいわれる。
○コケにする
虚仮。
○コッペパン
フランス語coupe、フランスのクーペというパンに見た目が似ていたのでクーペパン、訛ってコッペパン。
○五万米
カタクチイワシが大量に獲れ、余ったのを田圃の肥料とした。
○ごり押し
ごりは川魚(カジカ)など、川底にへばりついているので・網を川底に押しつけ強引に牽き進める。
○コンビーフ
塩漬け牛肉。
○サニーレタス
サニーは「日産サニー」が源。
○サラダせんべい
サラダ油のこと。
○さわりの部分
義太夫のいちばんの聞かせどころ。
○シーザーサラダ
1942年メキシコのチェザーレ・カルディーニ(Caesar Cardini)が、大勢の客に対応するためありあわせの食材で作ったといわれる。
○しこ名・相撲
元は醜名、たくましい・強いの意だった。
○しち面倒くさい
七には、「甚だしい・ひどい」の意味がある。
○しっぺ返し
座禅の「竹箆」が源。
○東雲
明け方の眺めが良かったので東雲(明け方・曉の意)。
○シバエビ
芝浦の海老。
○柴又
海に点在した島々、干潮の時には渡ることができたので「島また島」→島又→嶋又など経て→柴又。
○しば漬け
古くは柴葉漬け、紫蘇葉漬け。
○シベリア
本当のところは、解らない。
○しもた屋
仕度屋、しまった家・商売をやめた家が源。
○シュークリーム
フランス語chou(キャベツ)+英語cream。
○せつない
切なしが転訛。
○セピア
sepiaは暗褐色・セピア色、元々はラテン語で「甲イカ」(イカ墨で書いた絵が退色した状態)。
○せんろっぽん
繊羅蔔、大根などを細かく切る意。
○ソメイヨシノ
江戸時代末期染井村で、オオシマザクラとエドヒガンの交配により生まれた。
※当初は「吉野桜」とよばれた、元が一本だったので染井吉野はどれも同じ遺伝子を持ち・どの桜も同じ事を考えるので一斉に開花する
○大八車
明暦の大火後牛車大工が復興工事用に作った、一人で八人分運べるので「代八車」。 他に、長さが八尺なので大八車、など諸説ある。
○たぬきそば
種抜き天ぷら→種抜き→たぬき。
○ため口
「ため」は同い歳、古くは二つのサイコロの目が同じことから、後に同じ歳を「ため年」。
○だらしない
自堕落(しだら)が転訛(逆読み)したともいわれる。
○タラバガニ・ズワイガニ
鱈の漁場で穫れるのがタラバガニ、脚が細くてまっすぐな若枝(すわえ)に見えたのでスワエガニ。
○タルタル
フランス語tartar、タタール人の意。
○ダンクシュート
水などに浸すのがダンク(dunk)、パンやドーナッツをミルクやコーヒーカップに浸す行為に見立てた。
○タンクトップ
タンクは屋内プールのこと。
○チキンナゲット
nuggetは、貴金属の塊の意。
○チャキチャキ
嫡々が転訛。
○ちゃんこ鍋
インドネシア語のチャンプールcampurや、親方父ちゃんと一緒に食べる、などあるが解らない。
○チョコレートパフェ
フランス語parfait(英語perfect)、完璧なアイスクリームの意。
○ちょんまげ
「ゝ」に似ているから。
○テキ屋
古くの的屋を読み変えた、香具師は矢師を読み変えたといわれる。
○てっちり
鉄ちり、鉄は鉄砲の意。
○どさ回り・どさくさ
「どさ」とは流刑地「佐渡」の逆さ読み。
○とちる
栃麺棒、速く動かす動作が慌てているように見えた。
○どどめ色
桑の実の色(グンマ限定)。
○どんでん返し
元々は「強盗返し・がんどう返し」、歌舞伎で大道具を90度ひっくり返すさいに生じる音を太鼓の音で隠した。
○どんぶり勘定
前掛けの前部分にあるのが「どんぶり」。
○ナスのしぎ焼き・田楽
古くは、茄子の身をくり抜き・鴫肉をのせ・味噌をつけて焼いた。
○二束三文
古くは二足三文、江戸時代わらじ二足で三文まで値下がりした。
○ニタリ貝・ムール貝
胎貝の異名、その形状からニタリ貝(似たり貝)。
○にべもない
魚のニベの浮き袋からとる鰾膠、粘着質が強いので、粘りがない→あっさりしている→愛想がない。
○ねぎま
葱間、古くはマグロの「間」だった。
○ねこばば
「ばば」は、関西で言うババのこと。
○ハイジャック
hijack、飛行機・船・列車・バスなど、乗物全般に使われる。
○パウンドケーキ
材料が1ポンド(1pound)だった。
○はっけよい
八掛良い・はよきほへ・発気揚々、などの説がある。
○パッションフルーツ・トケイソウ
メシベが十字架に・オシベと萼が10人の使徒に見えるので、キリスト受難(passion)の花。
○バッテラ
ポルトガル語bateira、船の意。
○ハツとガツ・肉
heartsとgutsらしい。
○ハトムギ
鳩麦と八斗麦の説がある。
○ハマナス
ハマ梨が転訛したといわれる。
○はめをはずす
馬の口にくわえさせる「はみ」がはずれて、馬が暴れ出す様子。
○ハヤシライス
丸善創業者早矢仕有的考案の賄い飯とも、ハッシュドビーフが源ともいわれるが、本当のところは解らない。
○バラ肉
ローストしやすいのがロース肉、英語filletがヒレ、あばら骨についているのがバラ肉。
○バレーボール
valleyは、球が地につかないうちに打ち返すこと。
○ハンドウイルカ
動きが歌舞伎の半道のようなのでハンドウイルカ。
○ビー玉
ビードロ玉が源との説がある。
○ビキニ
マシャール諸島のビキニ環礁、衝撃的だった。
○左利き(酒飲み)
大工は右手に槌・左手にノミ、よって左手はノミ手。
○ひとしお
一入(ひとしお)、染物を染料に一回つけるのが一入、繰り返して鮮やかになる。
○ひとりぽっち
独り法師
○ピロリ菌
ピロリは幽門のこと。
○ブービー賞
欧米では最下位賞、日本では最初から最下位を狙う人がいるのでビリから二番目とした。
○フジツボ
形状が富士山に似ている。
○プラスアルファ
Xをαと見誤ったともいわれる。
○ベーゴマ
貝独楽、バイ貝が源。
○ぺーぺー
平平が源。
○へそくり
「綜麻繰り金」が源、昔に綜麻繰りを内職としてお金を貯めた。
○へそを曲げる
「へそ」は船の櫓の支点のこと。
○へのかっぱ
木っ端の火、簡単に燃えるの意。(カッパの屁の説もある)
○へんてこ
変梃、古く「へんちく」が転訛したといわれる。
○ぺんぺん草・ナズナ
口三味線の音がペンペン、ナズナの実が三味線の撥に似ている。
○ほうぼうのてい
「這う這う」が源。
○ほうれん草
ベルシャとネパールとの説がある。
○ほくそ笑む
北叟笑む、北の国に住む老人がひっそり笑ったが源。
○ポン酢
ポンはオランダ語pons(柑橘類)。
○マスクメロン・ジャコウウリ
ムスク(musk:麝香)の香りがするのでマスクメロン。
○まどろっこしい
間怠い→まだるこい、が転訛。
○まな板
古くは「真魚板」。
○みたらし団子
京都下鴨神社境内の茶店、御手洗川の名をとったといわれる。 当初は醤油の付け焼きだった。
○みっともない
「見苦しいものは見たくもない」が転訛。
○むしずがはしる
虫酸、胃液が逆流する様子から。
○めりはり
減り張り、古くは音の高低・強弱、後に歌舞伎用語。
○もっけの幸い
物怪、おばけの意。
○やんちゃ
「嫌じゃ」が訛ったとも、オランダ語説もある。
○ヤンママ
ヤンキーママのこと。
○ゆびきりゲンマン
拳万、一万回殴るの意。
○ランゲルハンス島
ランゲルハンスは人名。
○レトルト
本来は加圧加熱殺菌装置のこと、ガラス製実験器具が源。
○衣紋掛け
古くは衣服を正しく着るための作法が衣紋。
○一張羅
一張りの羅(薄物)。
○温州みかん
温州は中国の地名、日本みかんとの関係は無い。
○懐石料理
修行僧が寒さ・空腹を紛らわすため暖めた石を懐に入れたことから、禅宗で料理を意味する。
○海千山千
海に千年・山に千年住んだ蛇は竜になる。
○鴨なんばん・カレーなんばん
大阪難波は長ネギの産地だったので、難波→なんばん→南蛮となったとの説がある。
○関さば・関あじ
大分佐賀関で穫れた魚。
○金に糸目をつけない
凧表面につけた糸のこと、無いとどんどん上がっていく。
○九官鳥
江戸時代に中国から持ち込んだ人物の名。
○犬のポチ
英語spotty(斑点・ぶち)とも・フランス語petit(小さい)ともいわれる。
○胡瓜
胡の国で穫れた、黄瓜とも書く(黄色の意)。
○高野豆腐
江戸時代の高野山には「こおり豆腐屋」があった、今は無い。
○左官
古く宮中職人「木工寮の属(さかん)」が源。
○際物
季節が変わる間際に売り出された物だった。
○四六時
六時間×四回=24時間。
※太陽暦以前は、二六時で十二刻が一日
○縞模様
古くは「島もの」、南蛮貿易でアジア諸国から入ってきた布地にこの模様が多かった。
○助六寿司
歌舞伎助六由縁江戸桜に出てくる助六の愛人揚巻を、油揚げのいなりと海苔巻で表している。
○小松菜
江戸川区小松の産、徳川綱吉の好物だったらしい。
○小倉あん
鹿の背中の模様に似ているので、京都小倉山(奈良小倉山)をもじった。
○松ぼっくり
松ふぐりが訛ったといわれる。
○色物
寄席で出演者名を書いた「めくり」、落語家は黒文字・それ以外は色文字(朱文字)で書かれていた。
○食パン
菓子パンに対して食パン、食事用のパンでもある。
○辛子明太子
明太は朝鮮語でスケソウダラ。
○正念場
歌舞伎・浄瑠璃の「性根場」、性格の奥深い部分が表れている場面。
○西京漬け
東京に対して西京。
○折り紙付き
平安時代の公式文書、紙を半分に折っていた。
○舌平目
牛の舌に似ている。
○大盤ふるまい
「椀飯振る舞い」が源。
○単車
昭和初期、サイドカーが付くと復車・付かないと単車だった。
○段ボール
ボール紙boardを間違えてボール、らしい。
○男爵いも
明治時代、河田龍吉男爵がアイルランド原産の愛リッシュコブラを持ち帰り・改良した。
○地下足袋
じかたび、足袋に代わって登場・直に土を踏むので「直足袋」が源との説がある。
○朝っぱら
朝腹が源。
○長いものには巻かれろ
「長いもの」とは、古くは中国の伝説にでてくる象の鼻のこと。
○長丁場
宿場間の距離。
○帝王切開
ドイツ語kaiserschnittを誤訳したともいわれる。
○鉄火巻き
マグロ赤みが溶けた鉄色に似ているからとの説がある。
※賭博しながら、フツーの海苔巻き鉄だって食べられるが、鉄火丼は食べられない
○田作り
大量に穫れて余ったイワシを田んぼの肥料としたので、田を作る→田作り。
○南高梅
元は高田梅、和歌山県立南部高校の南を付けて南高梅。
○番茶
番は日常・普通の意、番傘・御番菜と同じつかいかた。
○百葉箱
中国古くは「牛や羊の胃」。
○幕の内弁当
芝居の幕が降りている間に食べる弁当。
○万引き
元々は間引き。
○面白い
顔面が白くなる→顔色が良くなる、が源。
※古くは、面白い=顔が白い=死人の顔、だった。 平安時代なると、宮殿の中は暗いので「白い顔」が美人の条件となった。
○毛嫌い
馬の毛色。
○野次馬
「親父馬」が源、年老いた牡馬のこと。
○柳川鍋
天保年間江戸横山同朋町「柳川」が始めたとの説がある。
○柚子胡椒
九州では、唐辛子を胡椒とよんでいた。
○与太郎
元々は浄瑠璃界の隠語。
○竜田揚げ
その色から、紅葉の名所・奈良竜田川にちなんで名付けた。
○扁桃腺
扁桃はアーモンドのこと。
○孫の手・まごのて
昔の中国は伝説の女仙人「麻姑」その爪は鳥のように長く、背中を掻いてもらうと気持ち良いだろう。 なので、背中を掻く棒を「まこ(まご)」・幼子の手のようにも見えるので「孫の手」とよばれるようになった。
○完璧
趙の王が持つ宝物「和氏の璧」を、泰の王が十五のまちと交換を申し出た。 断り切れずにいた趙の王を見た藺相如が使者として交渉に行き、璧を無事に持ち帰った。
※璧であり壁ではない
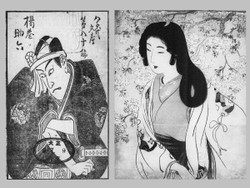



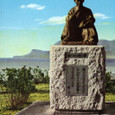
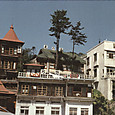
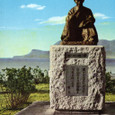





コメント