むかしむくれて 
鰻の辻売り
判じ絵
唐人飴売り
判じ絵
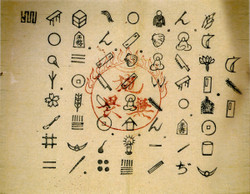 ○法華経(絵文字経)
○法華経(絵文字経)
ほ(帆)・け(げじげじ)・きよう(経)、
みょう(茗荷)・ほ(帆)・れんげ(蓮華)・きょう(経)
にょ(稲塚の方言)・ぜ(銭)・が(糸巻側)・も(牛)・ん
ぶつ(仏)・ざい(鋸の方言)・だい(ムロ)・しゅ(宋)
しょ(将棋)・ほう(棒)・ぢ・そう(僧)
かい(貝)・ぶつ(仏)・ち(乳)・け(げじげじ)・ん
いつ(一)・さい(さい、敷居の方言)・しゅ(宋)・じよう(状)
かい(貝)・じょう(状)・ぶつ(仏)・どう(堂)
にょらい(如来)・く(九)・お(尾)・ん
じょう(状)・ざい(鋸の方言)・りょう(料理の道具)・せん(銭)
きう(葱の方言)・よ(四)・じゅう(重箱)・しょ(将棋)
さん(三)・ぜ(銭)・や(矢)・く(九)・も(牛)・つ(杖)
だい(台)・し(朱宋)・かん(鐶)・き(木)
さ(桜)・ら(羅宇)・い(井)・に(二)・こ(香)


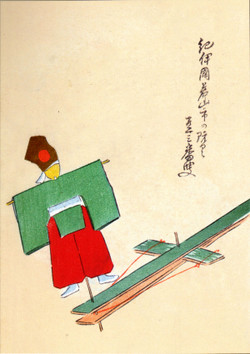









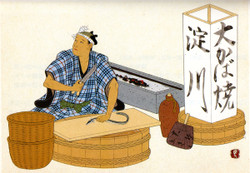
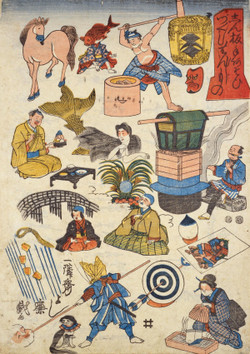


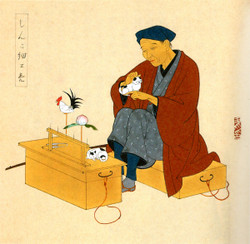
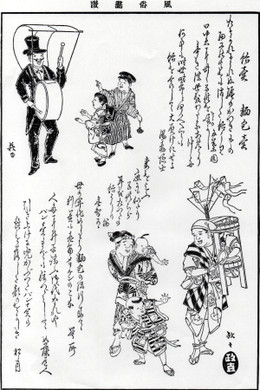
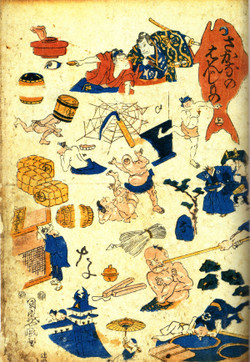


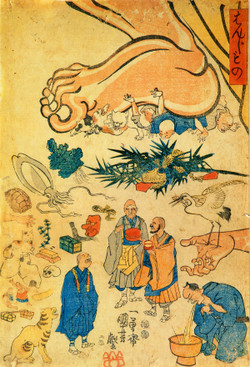
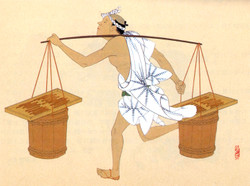

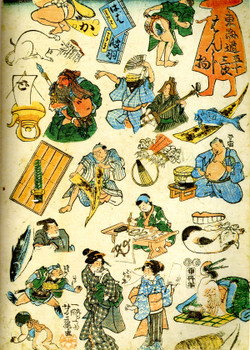
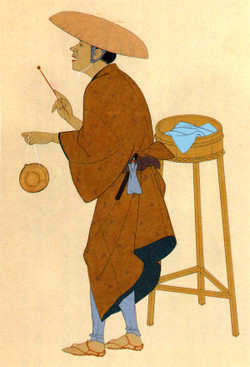
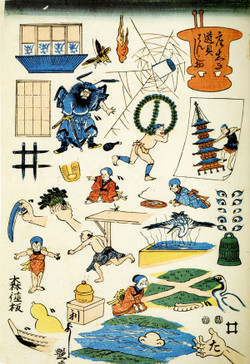

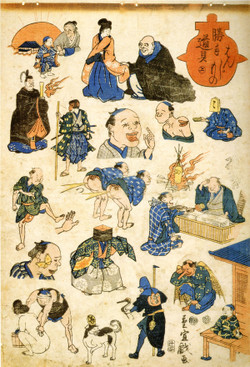


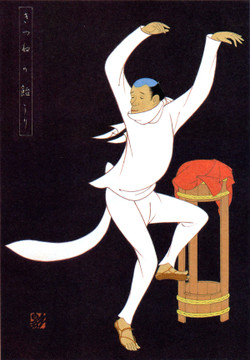




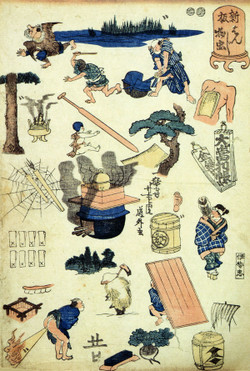

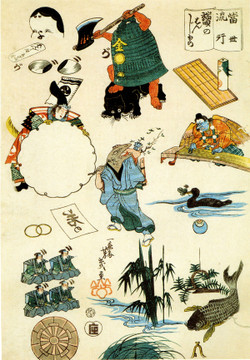

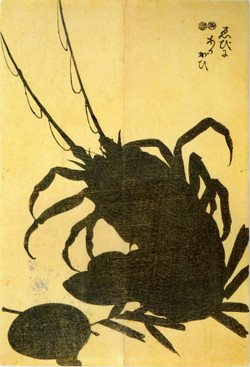
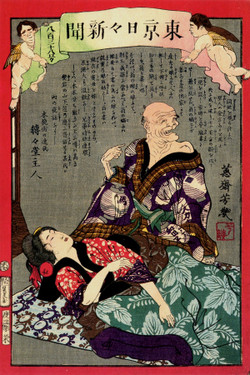
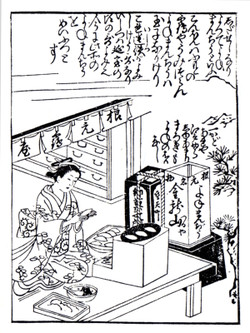
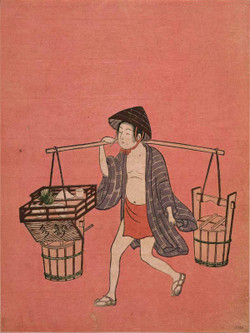
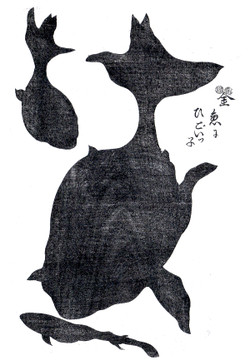


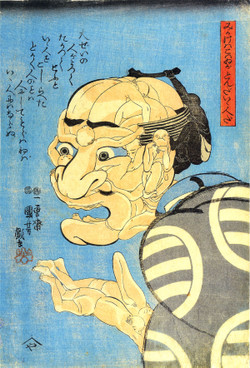




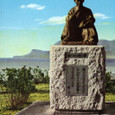
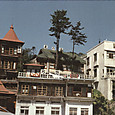
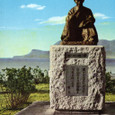





最近のコメント