ぐんま 
あずきとぎばばあ
グンマの昔:ロウ石山・下仁田
不二洞
グンマの昔:板倉の里神楽
引札:玩具提灯問屋
グンマの昔:神代文字
群馬での暮らし:ハタケシメジ
群馬での暮らし:正田醤油
群馬での暮らし:こぶ観音
引札:牛乳配達
グンマの昔:法師温泉
群馬での暮らし:おけら
群馬での暮らし:ホレステリンソーダ
シイタケ抽出エキスによる「しいたけ風味飲料」。 1970年発売、1992年消滅。 その後、ホレステリンオリゴ→スーパーホレステリンとなる。
※地域によっては「椎茸の塩漬け」もあった。






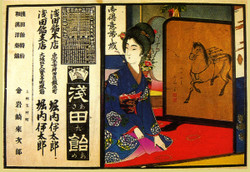




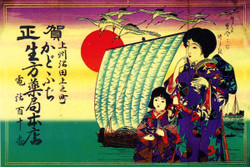
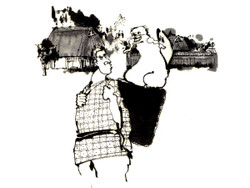






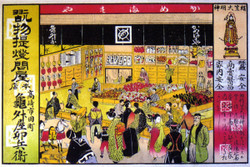


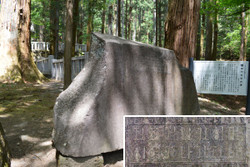










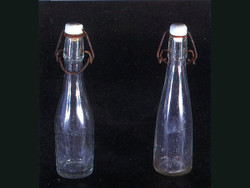
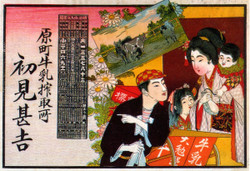



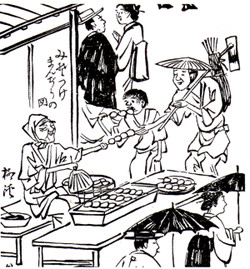


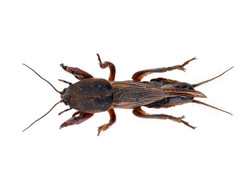



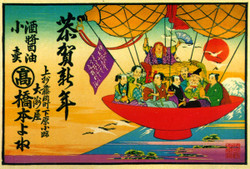
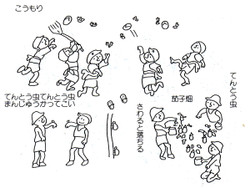


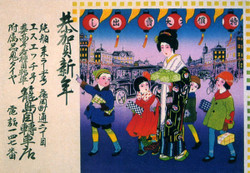



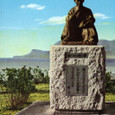
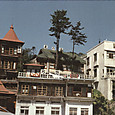
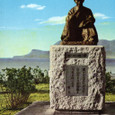





最近のコメント