ぐんま 
グンマの昔:オキヌサン
グンマの昔:四万温泉
群馬での暮らし:グンマの花見
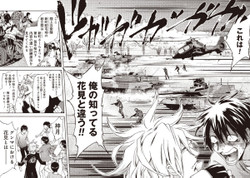 [お前はまだグンマを知らない]にもでてくる【グンマの花見】、いよいよ開戦。
[お前はまだグンマを知らない]にもでてくる【グンマの花見】、いよいよ開戦。
○新町創設63周年記念行事・新町桜まつり(高崎市主催)
開催日:2014年4月6日(日)
開催場所:新町駐屯地(群馬県高崎市)
○しんまち桜まつり
開催日:4月5日~6日、10:00~15:00
開催場所:陸上自衛隊新町駐屯地・桜並木
○相馬原駐屯地創立記念行事
開催日:2014年4月12日(土)
開催場所:相馬原駐屯地飛行場地区(群馬県北群馬郡)
グンマの昔:鎌原城
グンマの昔:天明の浅間焼け
グンマの昔:花敷温泉
グンマの昔:白石石灰採掘場
お菊伝説
五家宝
道祖神:中原村
グンマの昔:少将桜
猟師と山男
 《グンマを話そう》
《グンマを話そう》
○猟師と山男(霧積)
猟師が霧積の奥の岩場にトヤバを作って泊まり込んでいると、ある晩「今夜一晩泊めてくれ」と気味の悪い声がした。 そのうち、獣のような足が小屋の中に入ってきたので、アイクチで足を刺すと消えてしまった。 翌朝、川づたいでお湯の湧き出ている所に来ると、白髭の爺さんが足の傷をお湯で洗っていた。「悪いやつじゃなさそうだな。急いで家へかかえれ。子供が火傷しているからこの湯を汲んでいって洗ってやれ」
猟師が急いで家へ帰ると子供が大火傷をして泣いていたので、汲んできたお湯で洗うとみるみるうちに治った。 こうして「霧積の湯」は「猟師が見つけた傷によくきくお湯」といわれるようになった。
ぐんまわらべうた:こんにゃく毬
グンマの昔:高崎製紙
 ○高崎板紙株式会社・上毛製粉株式会社・東洋製粉株式会社
○高崎板紙株式会社・上毛製粉株式会社・東洋製粉株式会社
1914年麦ワラなどを使った板紙会社として高崎板紙創設(1949年高崎製紙 ・1975年閉鎖転業)、1918年小麦を原料とする製粉業を担う上毛製粉設立(翌年日清製粉と合併・1988年撤退)、1913年京都製粉所創立(後に日本製粉高崎工場・2012年閉鎖)。

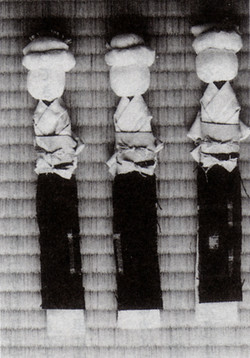
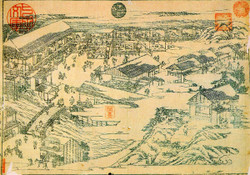
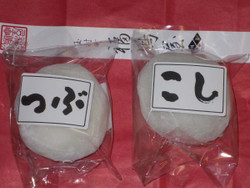


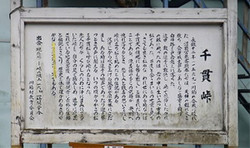

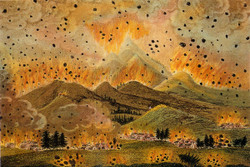



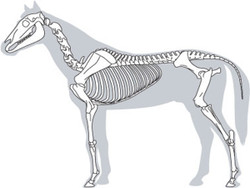


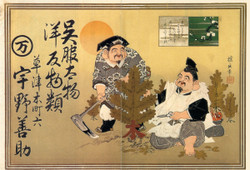
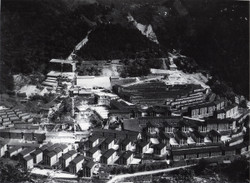









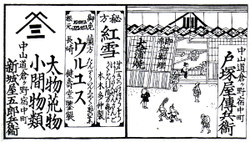



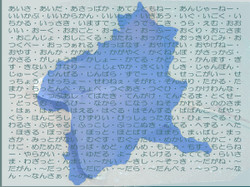



















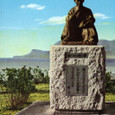
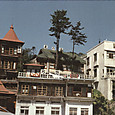
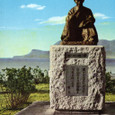





最近のコメント